国際叡愛総合芸術大学 研究活動の概要
国際叡愛総合芸術大学の研究活動は、「叡智と創造性の融合」という教育理念に基づき、伝統的な芸術研究と最先端のテクノロジー研究を融合させることを目指しています。単なる理論の探求にとどまらず、社会実装を視野に入れた実践的な研究を重視し、人類の未来に貢献する新しい芸術のあり方を模索します。研究活動は、学部と大学院の各研究室を中心に、学内連携プロジェクトや学外の研究機関、民間企業との共同研究を通じて多角的に展開されています。
研究体制
本学の研究体制は、以下の3つの主要な部門から成り立っています。
- 未来創造研究機構: 未来創造学部を基盤とする研究機関。特に、AIと人間の創造性に関する研究、メディアアート、インタラクティブアートの分野を専門とします。
- 芸術文化研究センター: 芸術学部を基盤とする研究機関。伝統的な絵画、彫刻、工芸、デザインなどの分野における技術継承と革新、芸術史、芸術理論の研究を主導します。
- 学際共同研究推進室: 学部・研究機構の垣根を越え、異なる専門分野の教員や学生が共同で研究を進めるための支援を行います。社会科学や人文学など、芸術以外の分野との連携も積極的に推進します。
主要な研究テーマ
本学の研究は、以下の4つの主要な領域に焦点を当てています。
1. AIと創造性のフロンティア研究 この領域では、人工知能を芸術創造のパートナーとして捉え、その可能性を多角的に探求します。
- テーマ例: 「感情認識AIによる音楽生成アルゴリズムの開発」
- 概要: 人間の表情や心拍数といった生体データをAIが分析し、リアルタイムで感情に呼応する音楽や映像を生成する技術の研究。これにより、観客と作品が相互作用する新しい形のライブパフォーマンスやインスタレーションを可能にします。
- テーマ例: 「デジタルツイン空間における芸術作品のアーカイブと展示手法の研究」
- 概要: 物理的な芸術作品をデジタル空間に再現し、劣化することなく永久に保存する技術の研究。これにより、世界中の人々がいつでもどこでも高精細なアートを鑑賞できるプラットフォームを構築します。
2. 伝統芸術と新技術の融合研究 伝統的な芸術技法をデジタル技術と組み合わせることで、その魅力を再発見し、新しい表現を生み出す研究です。
- テーマ例: 「古都アヤカの伝統工芸品におけるデジタルデザインの応用」
- 概要: 伝統的な染色や織物の模様をAIが学習し、無限のデザインバリエーションを生成するシステムを開発。これにより、職人の技術と最新のデザインを融合させ、現代のライフスタイルに合った新しい工芸品を創出します。
3. 社会実装型アート研究 芸術の力を社会課題の解決に活かすための実践的な研究です。
- テーマ例: 「環境問題をテーマにした参加型アートプロジェクトの効果検証」
- 概要: 市民が参加できるアートを通じて、気候変動やゴミ問題に対する意識を高める方法を研究。参加者の行動変容をデータで分析し、アートの社会的な影響力を科学的に証明します。
4. 芸術理論と哲学の研究 芸術とは何か、創造性とは何かといった根本的な問いを掘り下げる研究です。
- テーマ例: 「AI時代の美学と倫理」
- 概要: 人工知能が生成した作品を「芸術」と呼べるのか、その美的価値はどこにあるのかといった哲学的問いを探求。AIの創造活動における倫理的課題についても考察します。
研究成果の発表
- 年次研究発表会: 毎年、全教員と大学院生が参加する大規模な発表会を開催。研究成果をポスターセッションや口頭発表形式で共有します。
- 学術論文: 各分野の専門誌に論文を掲載することを奨励。特に、学際的な研究成果は本学独自のジャーナル「叡愛学術論叢」に発表されます。
- 「未来創造展」: 研究室単位で、研究成果を芸術作品として具体化し、一般に公開する展覧会を定期的に開催。市民や企業との交流の場となります。
研究推進のための支援体制
- 研究費助成: 独自の学内研究費制度を設け、特に独創的なテーマや若手研究者のプロジェクトを支援。
- 研究倫理委員会: AI、バイオアートなど、倫理的な配慮が必要な研究に対しては、専門委員会が審査と指導を行います。
-
外部資金獲得支援: 共同研究先とのマッチングや、公的機関からの研究費獲得に向けたサポートを提供します。
研究不正防止への取り組み
国際叡愛総合芸術大学は、研究活動における公正性と透明性を確保するため、以下の多岐にわたる取り組みを実施しています。これは、大学の理念である「叡智と愛」に基づき、真摯な学術探求を推進するために不可欠なものです。
1. 研究倫理教育の徹底 すべての教員、研究者、大学院生を対象に、研究開始時と定期的な研修を通じて研究倫理教育を実施します。研修では、データ捏造、改ざん、盗用(剽窃)といった不正行為の定義、事例研究、そしてそれを防ぐための具体的な手法について学びます。また、AIを活用した創作活動における著作権や倫理的課題についても重点的に扱います。
2. 厳格な研究データ管理 研究データの保管・管理に関する明確なガイドラインを策定し、全ての研究者に遵守を義務付けています。研究成果の再現性を担保するため、生データは所定のサーバーに厳重に保管され、データの編集履歴が追跡可能なシステムを導入しています。
3. 成果発表前のチェック体制 学術論文や作品の発表前には、複数の教員によるダブルチェック体制を設けています。特に、AI生成物を含む場合は、その生成プロセスや利用したデータの出所を詳細に記録し、不正の疑いがないかを厳しく検証します。
4. 内部通報窓口の設置 研究不正に関する疑いを匿名で報告できる独立した通報窓口を設けています。通報者は不利益を被ることがないよう保護され、通報された事案は速やかに調査委員会に付託されます。
機関内の責任体系の明確化
研究不正を未然に防ぎ、発生した場合には迅速かつ適切に対応するため、大学内の責任体系を以下のように明確に定めています。
1. 総括責任者:学長 大学全体における研究活動の公正性を最終的に統括する責任者です。研究不正防止のための基本方針を決定し、全学的な啓発活動を指揮します。
2. 統括管理者:未来創造研究機構長・芸術文化研究センター長 各研究機構・センターにおける研究活動の管理責任者です。所属する研究者への倫理教育の実施や、研究不正の疑いがある事案の初期調査を統括します。
3. 監査責任者:研究倫理委員会 研究倫理に関する専門的な第三者機関です。不正行為の通報があった場合、独立した立場で詳細な調査を行い、不正の有無を判断します。また、研究活動が倫理的規範に則っているか定期的に監査します。
4. 研究者個人の責任 研究活動を行うすべての教員、大学院生は、自己の研究の公正性に対して第一義的な責任を負います。研究データの正確な記録、引用・参考文献の適切な明記、そして倫理的課題への配慮は、各研究者の基本的な責務とされています。
これらの取り組みと責任体制は、この大学が学術的な信頼性を基盤に、未来に向けた芸術と研究を推進していくための重要な柱となります。
公的研究費の研究活動上の不正行為・不正使用の防止及び対応規程
公的研究費の執行に関する行動規範
本学の研究に携わる全ての教員および研究者は、研究費が国民からの貴重な税金によって支えられていることを深く認識し、高い倫理観をもって公正かつ誠実に職務を遂行するための行動規範を遵守します。
- 適正な執行の原則: 研究計画に基づき、研究目的に合致した経費のみを執行します。個人的な流用、架空取引、偽りによる請求、目的外使用は一切禁止します。
- 説明責任の遂行: 研究費の執行状況について、大学や外部監査機関からの求めに応じて、いつでも正確かつ透明性のある説明を行います。
- コンプライアンスの遵守: 公的研究費の配分機関が定める規程、法令、および本学の定める内部規程を厳格に遵守します。
不正防止計画の策定
研究費の不正を未然に防ぐため、大学全体で組織的な不正防止計画を策定し、継続的に改善を行います。
- 責任体制の明確化: 前述の通り、学長を総括責任者、各研究機構長を統括管理者とする明確な責任体制を構築しています。
- 不正リスクの評価と管理: 不正が発生しやすいリスク要因(例:研究費の不慣れな管理者、複雑な経理手続き)を定期的に評価し、そのリスクを低減するための対策(研修の強化、簡素な手続きの導入)を講じます。
- 啓発活動の実施: 研究者や事務職員を対象に、研究費の適正な使用に関する定期的な研修やe-ラーニングを実施し、意識向上を図ります。
研究費の適正な運営・管理
研究費の透明性と効率性を高めるため、以下の運営・管理体制を整備しています。
- 経理専門部署の設置: 研究費の管理を専門に行う部署を設置し、各研究者の経理処理をサポートします。すべての経費は、この部署の厳格な審査を経て執行されます。
- 電子化された執行管理システム: 研究費の申請、承認、執行、精算のプロセスを電子管理システムで一元化。これにより、不正な取引や不審な支出を自動的に検知し、リアルタイムでの監視を可能にします。
- 内部監査の強化: 定期的に内部監査を実施し、研究費の執行が規程通りに行われているか、不正行為の兆候がないかを厳しくチェックします。
不正行為に関する相談・告発
研究費の不正行為を早期に発見・是正するため、関係者が安心して相談・告発できる環境を整備しています。
- 専用の相談窓口: 研究倫理委員会内に、研究費の執行に関する疑問や不安を相談できる窓口を設けています。ここでは、専門の相談員が個別の事例に対して助言を行います。
- 独立した告発窓口: 不正行為の具体的な情報提供を受け付けるための独立した告発窓口を設置しています。告発者に関する情報は厳重に秘匿され、不利益を被ることはありません。
-
迅速な調査: 告発があった場合、速やかに予備調査を行い、必要に応じて研究倫理委員会が詳細な調査を開始します。不正が認定された場合は、厳正な処分を行います。
第三者機関等における研究成果の捏造、改ざん、盗用に関する告発等受付窓口は国の公的機関へ
【文部科学省関係】
文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課
文部科学省HPより受付
【日本学術振興会の実施する事業関係】
独立行政法人 日本学術振興会 監査・研究公正室
独立行政法人 日本学術振興会HPより受付
公的研究費についての相談
本学では、研究者が公的研究費の申請から執行、そして報告に至るまで、安心して研究に専念できるよう、専門的な相談窓口を設けています。この窓口は、研究費の使途に関する具体的な疑問、経費の計上方法、研究機関との連携手続きなど、幅広い相談に対応します。専門知識を持つ担当者が、各研究者の状況に応じた適切な助言を提供し、問題が複雑な場合は、経理部門や研究倫理委員会と連携して解決にあたります。
経過観察
研究費の適正な執行を確保するため、大学全体で継続的なモニタリングを実施しています。これは、不正を未然に防ぐための重要なプロセスです。
定期的なモニタリング
- 研究費の使用状況をシステム上でリアルタイムに監視し、不審な取引や頻繁な経費の修正がないかを確認します。
- プロジェクトの進捗報告書と研究費の使用状況を照合し、研究活動と経費が整合しているかをチェックします。
- 年に一度、研究費の監査を兼ねたヒアリングを実施し、研究者から直接、執行状況や課題について聴取します。
AIによる監査支援
- AI監査システムを導入し、膨大な経費データを分析。人間が見過ごしがちなパターンや異常値を検出し、不正の可能性を早期に発見します。これにより、監視の精度と効率性を飛躍的に向上させています。
研究倫理教育
全ての研究者と大学院生は、公的研究費に関わる研究を開始する前に、必修の研究倫理教育プログラムを修了することが義務付けられています。
- 基礎編: 研究費不正の定義、事例、関連法規、そして研究者の責任について学びます。
- 応用編: AIを用いた研究や共同研究における倫理的課題に焦点を当て、データ管理や著作権、利益相反の回避方法を具体的に習得します。
- 継続教育: 倫理観を維持し、最新の動向に対応するため、2年ごとに継続教育が必須とされています。
研究者登録システムへの登録
本学の研究者は、外部の公的研究費を申請するために、独自の「研究者登録システム」への登録が必須となります。
- 登録プロセス: 個人の研究業績、専門分野、過去の研究費獲得歴などをシステムに登録します。これにより、研究機関全体での研究者情報を一元管理し、適正な研究費の配分を支援します。
-
研究者番号: 登録完了後、個別に研究者番号が発行されます。この番号は、すべての公的研究費の申請と報告において使用されます。
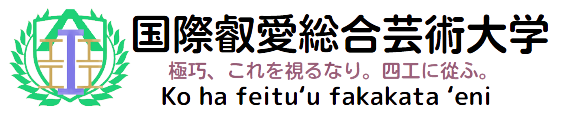
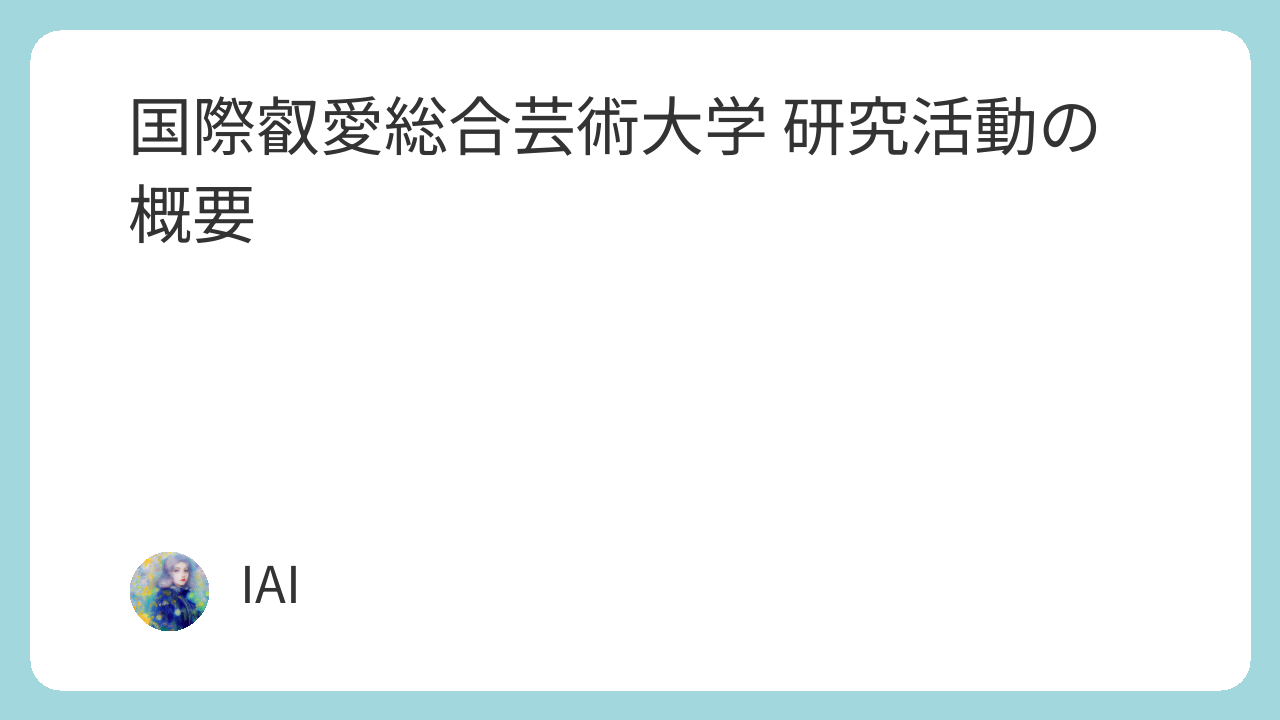
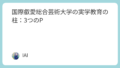

コメント